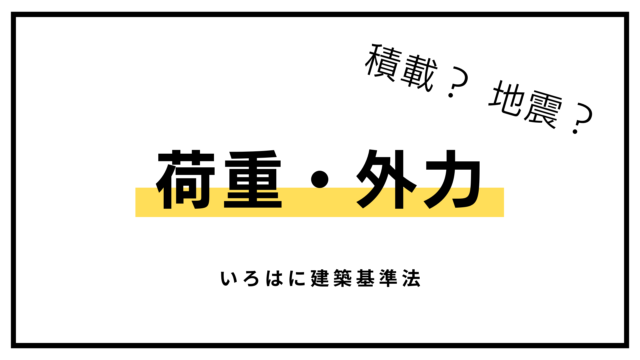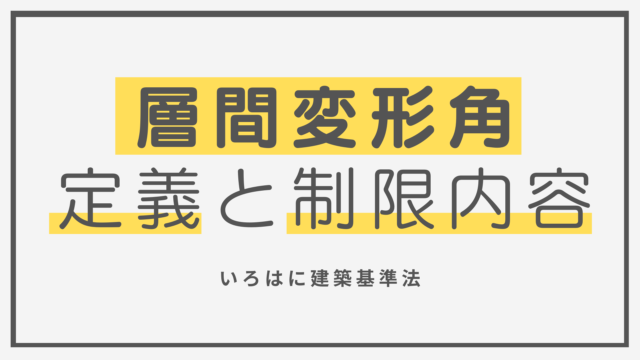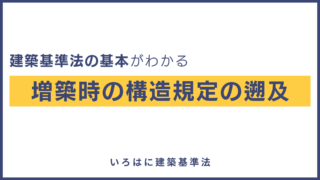1次設計と2次設計の目的の違い
1次設計と2次設計は、それぞれ構造計算の目的が異なります。
1次設計は、常時・稀(存在中数回程度)に遭遇する荷重・外力に対して損傷しないことを目的としています。常時の荷重・外力は、長期荷重といわれる荷重・外力です。稀に遭遇する荷重・外力は、短期荷重といわれる荷重・外力のうち暴風・積雪・中地震(C0=0.2相当)時の荷重・外力です。
2次設計は、極稀に遭遇する荷重・外力に対して倒壊・崩壊等しないことを目的としています。極稀に遭遇する荷重・外力は、短期荷重のうち大地震時の荷重・外力です。

\ まずはこの本から!! 構造関係規定の解説書 /
1次設計
1次設計の計算基準は、次の計算基準で構成され、構造計算方法(ルート1〜3)によらず同様の構造計算基準が適用されます。
| 計算項目 | 条項 | |
|---|---|---|
| 1 | 許容応力度計算 | 令第82条第1〜3号 |
| 2 | 使用上の支障が起こらないことの確認 | 令第82条第4号 |
| 3 | 屋根ふき材等の構造計算 | 令第82条の4 |
※高度な構造計算方法である時刻暦応答解析・限界耐力計算については若干異なります。(ここでは割愛します。)
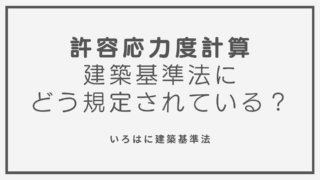
【わかりやすく解説】許容応力度計算(建築基準法)
建築基準法における許容応力度計算の目的
許容応力度計算は、建築基準法において、建築物の構造計算の基本となる構造計算手法です。1次...
2次設計
2次設計の計算基準は、建築物の規模等により適用する構造計算方法(ルート)により異なります。目的は「大地震に対して倒壊・崩壊等しないこと」で同様ですが、小規模な建築物については比較的簡易な計算基準を適用することができますが、大規模な建築物については高度な構造計算基準が適用されます。
例えば、保有水平耐力計算(ルート3)の2次設計部分の構造計算基準はがについては、次の2つの計算基準です。
| 計算内容 | 条項 | |
|---|---|---|
| 1 | 層間変形角の確認 | 令第82条の2 |
| 2 | 保有水平耐力 ≧ 必要保有水平耐力の確認 | 令第82条の3 |
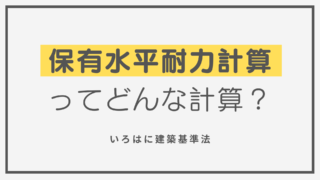
【わかりやすく解説】保有水平耐力計算(令3章8節1款の2)
法令集が手元にある方は、法令集を読みながら解説を読み進めると、一層、理解が深まります。
この解説では次の疑問に答えます!!
...
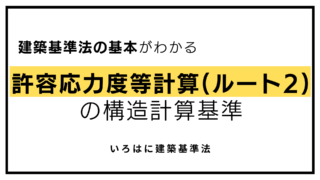
【建築基準法の基本がわかる】許容応力度等計算(ルート2)
法令集が手元にある方は、法令集を読みながら解説を読み進めると理解が深まります。
許容応力度等計算は、5つある構造計算基準のひ...

【わかりやすく解説】鉄骨造の構造計算ルート1-1,1-2,1-3(R7.4.1改正対応)
鉄骨造ルート1の構造計算基準は令和7年の改正により、これまでのルート1-1、ルート1-2の2つルートに加えルート1-3が新たにできまし...
\ まずはこの本から!! 構造関係規定の解説書 /
▼▼ フォローしていただけると嬉しいです ▼▼