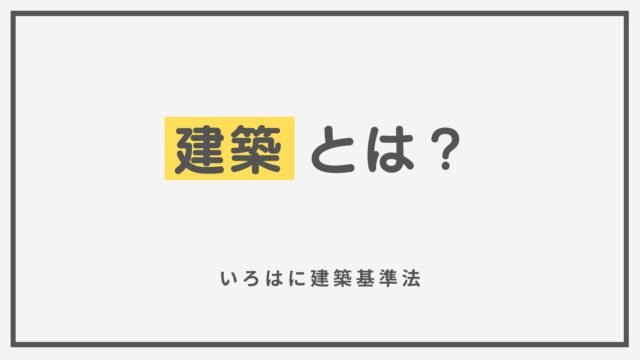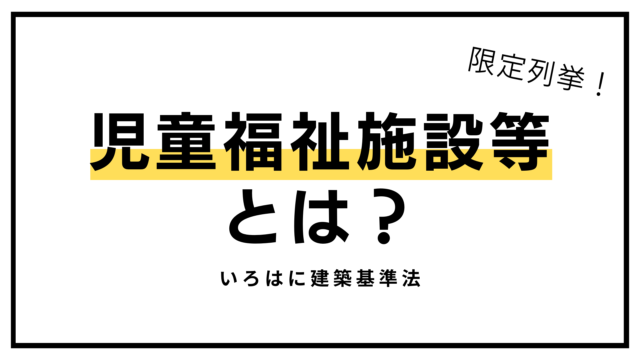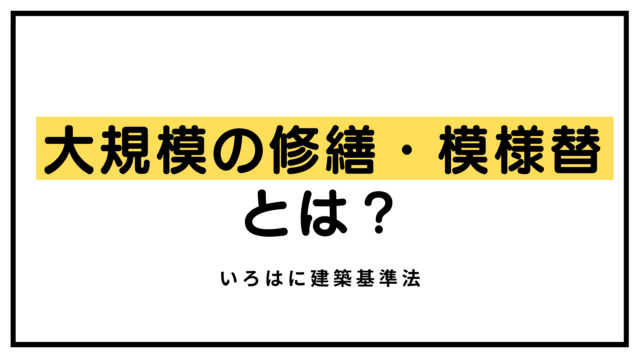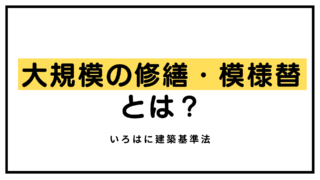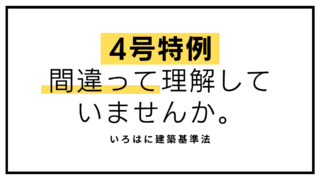この解説では次の疑問に答えます!!
- 既存不適格とは?
- 既存不適格建築物とは?
- なぜ既存不適格建築物が存在する?
- 既存不適格建築物と違反建築物の違いは?
- 既存不適格建築物を増築する際の注意事項は?
「既存不適格」とは
「既存不適格」とは「既に建っている建築物が、建築時の建築基準法の規定には適合しているが現行の建築基準法に適合していない状態のこと」です。
「既存不適格建築物」とは
「既存不適格建築物」とは「既存不適格の部分を有する建築物」です。
注意
既存の建築物でも、既存不適格の部分を有しない建築物は、現行の基準に適合している建築物ということですので、既存不適格建築物ではありません。
既存不適格建築物が存在する理由
大きく2つの理由があります。
- 建築基準法令の規定が改正されて基準が強化された
- 都市計画等が変更されて規制が強化された
❶について例えば、S56年の法改正で構造計算基準(耐震基準)が改正され、基準が強化されました。この改正前の耐震基準を旧耐震基準といい、改正後の耐震基準を新耐震基準といいます。改正前に旧耐震基準で建築された新耐震基準に適合しない建築物は法第20条についての既存不適格建築物です。
また、❷について例えば、建築時の敷地の建蔽率の上限が都市計画で指定された60%で建築された建築物が、都市計画が変更され指定建蔽率が50%になり、適合しなくなった建築物は法第53条の既存不適格建築物です。
既存不適格と違反は違う
既存不適格(既存不適格建築物)は違反(違反建築物)かということそうではありません。既存不適格建築物は法第3条第2項で認めれています。
第3条第2項 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際 現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が これらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、 当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、 当該規定は、適用しない。
参考
建築基準法に限らず、法令は、既に発生し成立した状態のものに対して新しい法令を、その施行の時点よりも遡って適用すること(遡及適用)は、原則ありません。このことは一般的に「法令不遡及の原則」といいます。
既存不適格が認められない場合
法第3条第2項に該当する場合でも、法第3条第2項が適用できない(認められない)場合もあります。法第3条第3項第1号〜5号のいずれかに該当する場合です。
| 法第3条第3項 | 既存不適格が認めれない場合 |
|---|---|
| 第1号 | 法改正前の基準に違反している建築物・その敷地 |
| 第2号 | 都市計画の変更などの場合に、変更後の制限に相当する従前の制限に違反している建築物・その敷地 |
| 第3号 | 法改正後に増築等を行った建築物・その敷地 |
| 第4号 | 法改正後に増築等を行った建築物の部分・その敷地の部分 |
| 第5号 | 既存不適格建築物だったが現行の規定に適合することになった建築物・その敷地、建築物・その敷地の部分 |
増築等する場合は現行規定が遡及される
既存不適格建築物を増築等する際には、表2にあるように法第3条第3項第3号により既存不適格となっている部分は、原則、現行規定が遡及適用されます。
ただし、法第86条の7によって、一部の規定については現行規定の遡及適用が緩和されます。
まとめ
- 既存不適格とは、基準時の建築基準法には適合しているが、現行の建築基準法の基準に適合していないこと
- 既存不適格建築物とは、既存不適格の部分を有する建築物です。
- 既存不適格建築物が存在するのは、法改正等により基準が厳しくなることがあるためです。
- 既存不適格建築物は、建築基準法で認められており、違反建築物とは異なります。
- 既存不適格建築物を増築すると、既存不適格部分につていも原則現行基準に適合することが必要です。ただし、一部の規定については、緩和が認めれています。