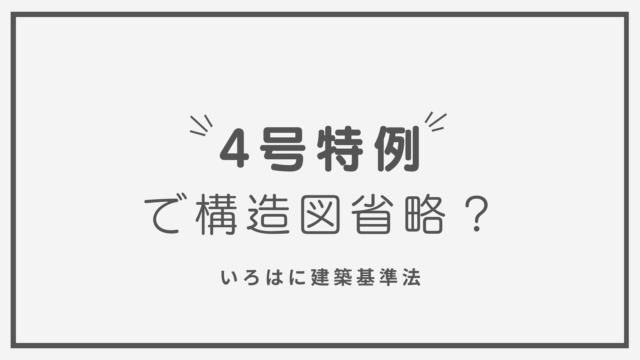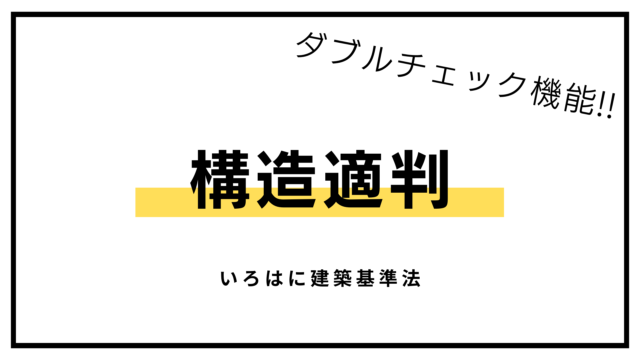令和7年4月1日の改正で6条区分が改正されさことにより、法6条の4に基づく審査の特例を適用することができる木造建築物の規模が縮小されました。今回はこの法6条の4に基づく審査の特例(いわゆる新3号特例)について、改正内容を含めて、下記の目次の順にわかりやすく解説していきます。
【1】新3号特例とは(概要)
新3号特例とは、法6条の4,1項3号により「設計士が設計した6条区分が新3号建築物の建築確認申請において、一部の規定の審査が省略される制度のことです。
審査が省略されるということは、建築確認申請の際に特例対象規定の審査に要する図書の添付省略することができるということでもあります。
なお、法7条の5により審査が省略される規定は完了検査・中間検査においてもの検査が省略されます。
- 6条区分についての解説はこちら(R7.4.1改正対応)
- 法第6条(確認申請)の法文読解(R7.4.1改正対応)←法文読解に特化した解説をしていますので併せて読むと理解が深まります
\ 令和7年4月1日改正も対応!! 建築基準法解説本の定番 /
【2】新3号特例が適用できる建築物
新3号特例が適用できる建築物は、建築士が設計した「6条区分が新3号建築物」の建築物です。新3号建築物とは、「法6条1項3号に該当する建築物」で、具体的には「平屋(階数1)で延べ面積200m2以下の建築物」です。

【3】審査が省略される規定
「審査が省略される規定」は、令10条3号、4号で定められる「建築場所」と「建築物の用途」による区分により異なります。
| 令10条の区分 | 6条区分 | 設計者 | 建築場所 (防火・準防火地域) | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 令10条3号 | 新3号建築物 | 建築士 | 防火地域・準防火地域以外の区域 | 一戸建ての住宅(※) |
| 令10条4号 | 新3号建築物 | 建築士 | 上記以外の建築物 (=防火地域または準防火地域で一戸建ての住宅(※)以外の建築物) | |
| (※) 住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の1/2以上であるもの又は50m2を超えるものを除く。 | ||||
| 特定対象の規定(法) | 令第10条第3号の建築物 | 令第10条第4号の建築物 |
|---|---|---|
| 法20条 (第1項第4号イに係る部分に限る。) | ○ | ○ |
| 法21条 | ○ | ○ |
| 法22条 | ○ | ー |
| 法23条 | ○ | ー |
| 法24条 | ○ | ー |
| 法25条 | ○ | ー |
| 法26条 | ○ | ー |
| 法27条 | ○ | ー |
| 法28条1項、2項 | ○ | ○ |
| 法28条3項、4項 | ○ | ー |
| 法29条 | ○ | ○ |
| 法30条 | ー | ○ |
| 法31条1項 | ○ | ー |
| 法32条 | ○ | ○ |
| 法33条 | ○ | ○ |
| 法35条 | ○ | ー |
| 法35条の2 | ○ | ー |
| 法35条の3 | ○ | ー |
| 法37条 | ○ | ○ |
| 法39条 | ○ | ○ |
| 法40条 | ○ | ○ |
| 法41条 | ○ | ○ |
| ○:特例対象、ー:特例対象でない(=審査対象) | ||
| 特例対象の規定(令) | 令第10条第3号の建築物 | 令第10条第4号の建築物 |
|---|---|---|
| 令2章 (令20条の3、令1節の3、令32条、令35条除く) | ○ | ○ |
| 令20条の3 | ○ | ー |
| 令3章 (令8節除く、令80条の2ついては大臣が指定するもの((H19国交告第1119号)) | ○ | ○ |
| 令4章 | ○ | ー |
| 令5章 (令119条除く) | ○ | ー |
| 令119条 | ○ | ○ |
| 令5章の2 | ○ | ー |
| 令5章の4 (令129条の2の4,1項6号・7号除く) | ○ | ○ |
| 令129条の2の4,1項6号・7号 | ○ | ー |
| 令144条の3 | ○ | ○ |
| ○:特例対象、ー:特例対象でない(=審査対象)、(※):国道交通大臣が指定するもの(H19国交告第1119号) | ||
構造耐力関係規定の特例
法第20条の構造(構造耐力)関係の規定については設計士が設計した全ての新3号建築物に適用できるわけではありません。構造方法(木造、鉄骨造またはそれ以外の特殊の構造方法の建築物)により次のいずれか条件を満たす必要がります。通称「仕様規定ルート」といわれるもので構造計算が不要なルートです。また、令第80条の2による特殊の構造方法については、一部の構造方法を適用する仕様規定ルートしか特例対象となりません。
| 構造方法 | 特例対象となる条件 |
|---|---|
| 令第3章第3節〜第7節の構造方法 | 法第20条第1項第4号イに関わる部分であること(仕様規定ルート) |
| 令第80条の2による特殊の構造方法 | H19国交告第1119号第1〜第4に関わる部分であること (プレストレストコンクリート造、WRC造、枠組み壁工法・木質プレハブ構造、アルミニウム号金造の仕様規定ルート) |
【4】新3号建築物(改正後)と旧4号建築物(改正前)の比較
改正前後での新3号特例(旧4号特例)を適用できる建築物の比較(=新3号建築物と旧4号建築物の比較)すると高さについては緩和されますが、階数・延べ面積については厳しくなります。
国内の多くの木造2階建の戸建て住宅は、旧4号特例が適用を受けることができましたが、2階建の時点で新3号特例の適用ができなくなってしまいます。
| 適用条件 | 新3号建築物 | 旧4号建築物 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 1 | 2以下 | 厳しくなった |
| 高さ | 16m以下 | 高さ13m以下 かつ 軒高9m以下 | 緩和された |
| 延べ面積 | 200m2以下 | 500m2以下 | 厳しくなった |
特定木造建築物の審査の合理化
6条区分の改正によって「国内の多くの木造2階建の戸建て住宅は、旧4号特例が適用を受けることができましたが、2階建の時点で新3号特例の適用ができなくなってしまいます。」では厳しすぎるということで、一部の構造図等を省略することができる規定が創設されました。(規則第1条の3)
適用できる建築物は次の表の特定木造建築物に該当建築物で、仕様表(チェックリストのようなもの)を添付することで一部の構造図等の添付を省略することができます。
| 規模 | 構造耐力規定の適用ルート | |
|---|---|---|
| 特定木造建築物 | ①〜③の全てに該当 ① 高さ16m以下 ② 階数2以下 ③ 延べ面積300m2以下 | 仕様規定ルート |