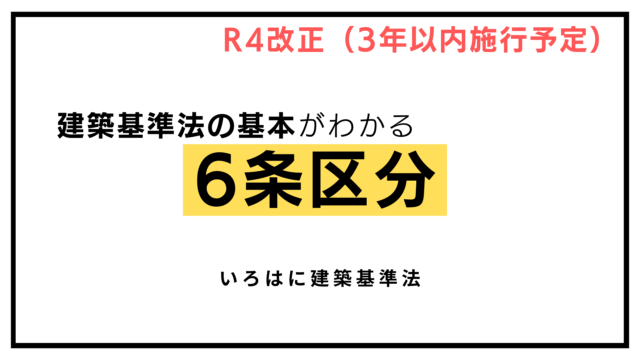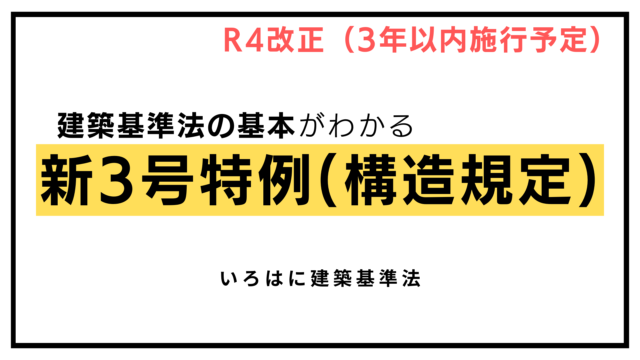この解説では次の疑問に答えます!!
- 特定木造建築物とは何か?
- 何が合理化される?
- なぜ令和7年4月1日の改正で創設されたのか❓
↑↑ 令和7年4月1日改正も対応!! 建築基準法解説本の定番 ↑↑
「特定木造建築物」とは
特定木造建築物とは、構造種別が木造で、構造計算をせず仕様規定ルートで構造耐力の安全性を確認した建築物のことで、建築基準法施行規則第1条の3第1項第1号イ(2)に定義が定められています。
建築基準法施行規則第1条の3第1項第1号イ(2)
確認に係る建築物又は建築物の部分が木造の建築物(法第6条第1項に規定する建築基準法令の規定(国土交通大臣が定めるものを除く。)に定めるところによる構造計算によつて安全性を確かめたものを除く。以下この項及び第3条の2第1項第十号において「特定木造建築物」という。)又はその部分である場合 次の表1の(は)項に掲げる図書のうち基礎伏図、各階床伏図及び小屋伏図
| 規模 | 構造耐力の適用ルート | |
|---|---|---|
| 特定木造建築物 | ①〜③の全てに該当 ① 高さ16m以下 ② 階数2以下(地階除く) ③ 延べ面積300m2以下 | 仕様規定ルート |
「特定木造建築物」の「確認申請の合理化」とは
特定木造建築物の確認申請の合理化とは、確認申請において、仕様表を添付することで軸組図などの一部の図面の添付を省略することがでる制度のことです。省略できる図書については以下の表のとおりです。
規則第1条の3第1項第1号イ表1関係の省略できる図書
| 仕様表の添付で省略できる図書 |
|---|
| 基礎伏図 各階床伏図 小屋伏図 |
規則第1条の3第1項第1号ロ表2関係の省略できる図書
| 仕様表の添付で省略できる図書 | 仕様表に明示すべき事項 | |
|---|---|---|
| 令第3章第2節 | 基礎伏図 | 基礎の構造方法、寸法並びに材料の種別及び寸法 |
| 令第3章第3節 | 基礎伏図 各階床伏図 小屋伏図 2面以上の軸組図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の形状及び寸法 |
特定木造建築物の創設の理由って?
特定木造建築物の確認申請の合理化が創設された理由は、法6条の改正によって法第6条の4第1項第3号による新3号特例(旧4号特例)の適用できる木造建築物の規模の縮小化です。
規模の縮小化のなかでも最も大きく影響しているものは階数です。その理由は、国内の多くの戸建て住宅は木造地上2階建であるためです。この木造地上2階建ての戸建て住宅の多くは、改正前は旧4号特例の対象でしたが、改正後は木造でも地上2階建となった時点で、6条区分が新2号建築物となり、新3号特例の適用を受けれなくなっていまいます。
このような新3号特例(旧4号特例)の対象でなくなってしまった木造建築物の建築確認申請の合理化を目的として創設されました。
こうなると、なぜそもそも6条区分を改正する必要があったのかという話になってしまいますが、この話をしだすと長くなるためここでは割愛させていただきます。
- 6条区分についての解説はこちら(R7.4.1改正対応)
- 法第6条(確認申請)の法文読解(R7.4.1改正対応)←法文読解に特化した解説をしていますので併せて読むと理解が深まります