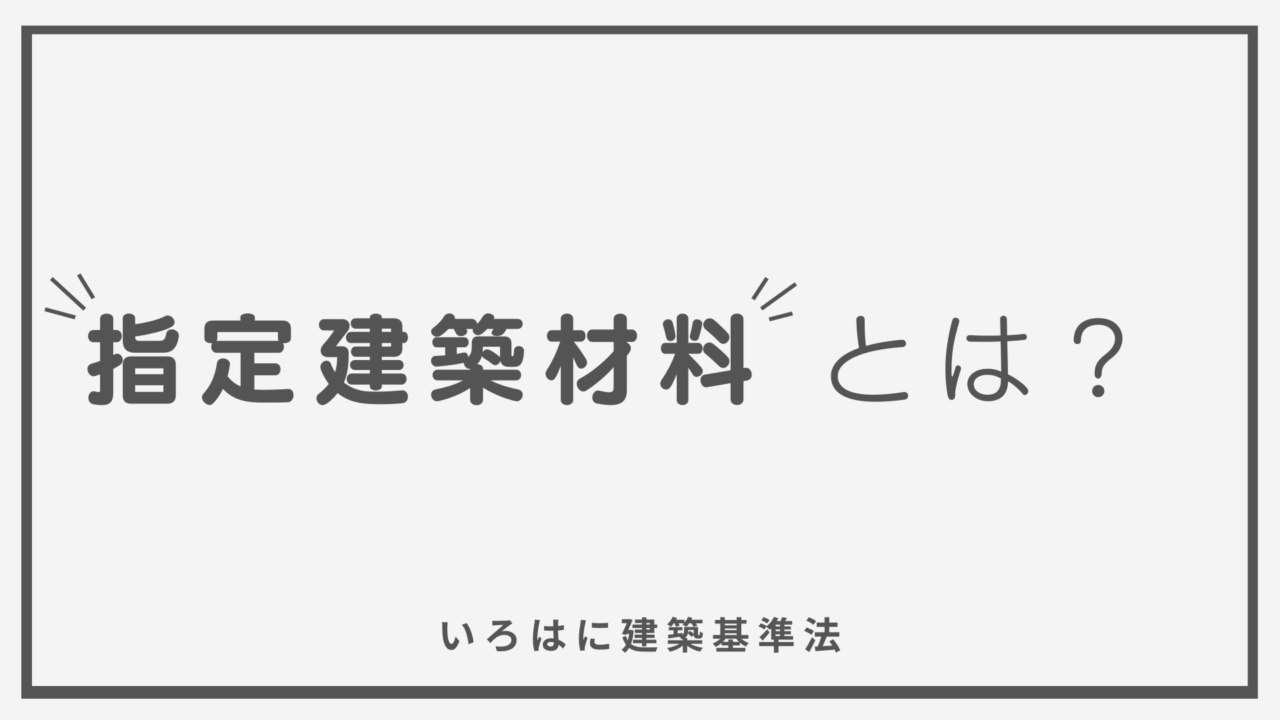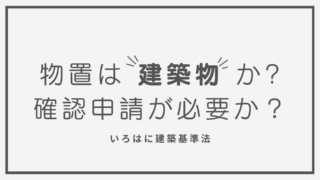建築物に使用する材料は、どんな材料を使用してもいいわけではありません。法第37条で使用する材料を制限しています。
ただ、建築物に使用するすべての材料について法第37条の制限が適用されるわけではありません。わかりやすく解説します。
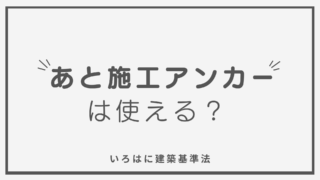
\ 設計・審査の実務から資格取得まで! 建築基準法解説本の大定番 /
概要
まずは概要です。イメージをつかみましょう。
法37条では、建築物を構成するうえで重要な部分【条件1】で、かつ、指定されている材料(指定建築材料)【条件2】については、一定の品質の材料を使用しましょう。ということをいっています。

図でイメージするとわかりやすいと思います。
ポイント大きく2つあります。
1 「法第37条が適用されるかどうか」の条件は2つある
2 重要な部分に指定建築材料を使用しなくていい場合もある
解説
それでは関係条文を掲載し、その後で、法37条が適用される【条件1】と【条件2】について、そして、法37条が適用されるものについてはどんな材料を使用しなければならないのかを解説し、最後に、JIS適合品についてのちょっとしたポイントを解説します。
関係条文
関係条文は法第37条、令第144条の3、H12建告1444号、H12建告第1446号です。法37条以外の条文の掲載は割愛します。
建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分(→令第144条の3)に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)(→H12建告第1446号第1)は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
第一号 その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する(→H12建告第1446号第2)日本産業規格又は日本農林規格に適合するもの
第二号 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める(→H12建告第1446号第3)安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの
【条件1】建築物の重要な部分とは?
① 基礎
② 主要構造部
1項本文に規定されています。
③ その他安全上・防火上・衛生上重要で政令で定める部分(→令第144条の3)
3つです。
③については、令144条の3で規定され、さらに一~六号の6つに分けられます。
一号 構造耐力上主要な部分で基礎・主要構造部以外の部分(←基礎・主要構造部は法37条1項本文で既出のため除かれているだけです。)
二号 耐火構造・準耐火構造・防火構造で主要構造部以外の部分(←主要構造部は法37条1項本文で既出のため除かれているだけです。)
三号 令109条に定める防火設備・これらの部分
四号 内装・外装の部分で安全上・防火上重要であると国交大臣が定めるもの(H12建告第1444号第1)
五号 主要構造部以外の、間仕切壁・揚げ床・最下階の床・小梁・庇・局部的な小階段・屋外階段・バルコニー・その他これらに類する部分で防火上重要であると国交大臣が定めるもの(→H12建告第1444号第1)(下線部分は法2条五号の主要構造部から除かれる部分と似ています。構造上重要と防火上重要の違いがあります。)
六号 建築設備・建築設備の部分(他法令で定められているもの・国交大臣が定める部分の除外規定あり。)
【条件2】指定建築材料とは?
H12建告第1446号(以下「告示」)第1各号に規定されています。
現在はH30.6.14に告示の改正があり二十三号が追加され一号~二十三号まであります。
一号 構造用鋼材・鋳鋼
二号 高力ボルト・ボルト
…
二十三号 直行集成材
告示第1の本文中に例外規定がありますので注意してください。この例外規定にあてはまる部分は法37条の制限を受けません。(本文の記載は割愛します。)
H30.6.14の改正で二十三号(直行集成材)が追加された際に、第1の本文にただし書きも追加されました。
3つあります。
- 時刻歴応答解析によって構造計算を行い、大臣認定を取得した建築物(構造安全上の観点で指定された建築材料(技術的助言))
- 法85条5項の仮設許可を受けた建築物
- 既に適法なものとして建っている建築物(いわゆる既存不適格ではないので注意してください。既存不適格については改めて解説します。)
については、告示の適用が除外されます。上記の建築物には、建築材料の指定がないということになります。
一定の品質の材料とは?
法37条一号か二号に適合するものでなければなりません。
一号に適合するもの
指定建築材料ごとに国交大臣が指定するJISまたはJASに適合するものと規定されていて、具体的にはH12建告第1446号第2に規定されています。
単に、JISに適合するものであればよいというものではなく、
例えば、告示第1第一号では
主要構造部の柱に使用する鋼材は指定建築材料になっており、第2別表第1によりJIS G3101の製品を使用する。といった感じで、材料ごとに指定されたJISに適合するものでなければなりません。
二号に適合するもの
指定建築材料ごとに国交大臣が定める技術的基準に適合するものとして国交大臣の認定を受けたものと規定されています。
認定とは、法37条二号の認定でなければなりませんので注意してください。
認定を受けたものとは、告示第3で示された技術的基準に適合するものということなのですが、各材料のメーカーが製品ごとに個別で国交大臣の認定を受けたものということです。
例えば、告示第1第十八号では
屋根に使用する膜は法37条二号に基づく認定を受けた材料を使用する。
といった感じです。
重要な部分への指定建築材料の使用は必須ではない?
冒頭のポイントの2つ目についてです。
例えば、一般的な木造住宅で柱・梁に木材(製材)を使用しますが、木材は指定建築材料に指定されていません。だからといって使用できないわけではなく、柱・梁は主要構造部で重要な部分ではあるのですが、木材は指定建築材料ではないので、法第37条第一号または第二号に適合させる必要がないということになります。
ただ、他の条文(令第37条、令第41条など)による制限はありますので注意してください。
JIS適合品について
JIS適合品については注意点があります。
法37条第一号では、品質がJIS(日本産業規格)(またはJASS(日本農林規格))に適合する必要がありますが、JISマークのついたJISマーク表示製品である必要はありません。
JISマークはJISの登録機関から認証を受けたものにしか表示できません。JISの規格に適合するものでもJISの認証を受けているとは限りません。
よってJIS適合品とJISマーク表示製品はイコールではありません。
https://www.jisc.go.jp/newjis/cap_index.html
ただ、現実はJISマーク表示製品ではないが、JIS規格適合に適合しているというものはあまりないと思われます。JISは出来上がった製品だけでない製品をつくるうえでの品質管理なども含めて認証を受けることになるためです。
あるとすると、海外の製品を使用したいという施主の希望があったときにその製品がJISマーク表示製品ではないが、海外の規格がJISの規格にも適合している(同等とみなせる)ものであれば使用できるといったことがあるかもしれません。
国交省から以下の技術的助言が発出されています。
令和元年6月28日 国住指第648号(令和元年6月28日 事務連絡)
この技術的助言ではGB規格(中国のJIS規格のようなもの)でミルシートなどで品質が確認できれば法第37条に適合するものとして扱ってもいいよ。
というものです。
(そもそも、この扱いには疑問が残りますし、コンテナの建築物への転用については、法37条だけでなく法20条の問題もありますが…。一応、国土交通省が出しているものですので参考にはできると思います。)
▼▼ 「建築基準法」の有益な情報を発信中 ▼▼