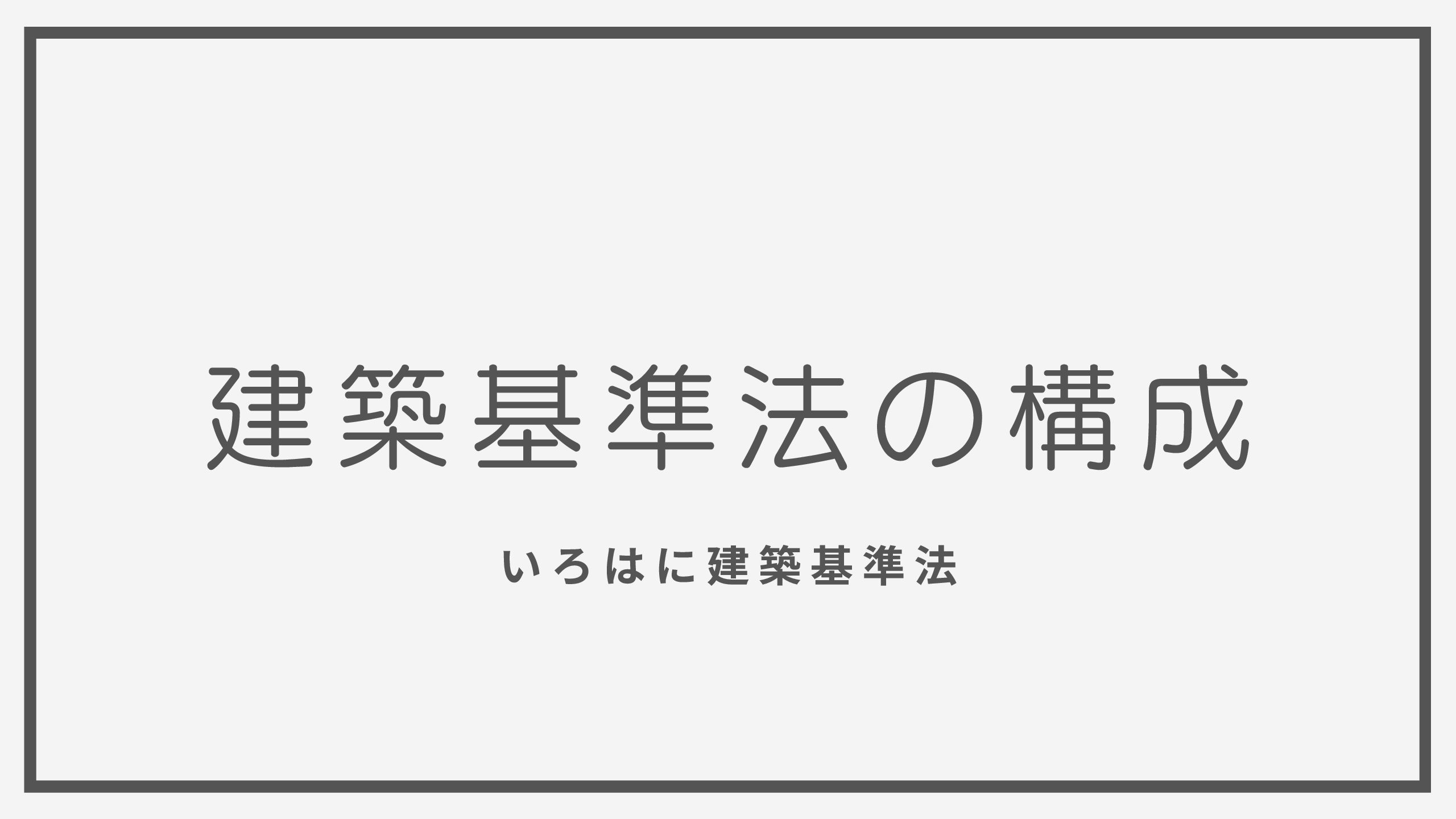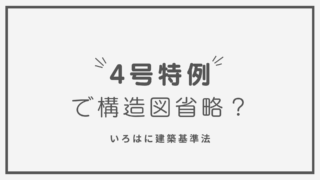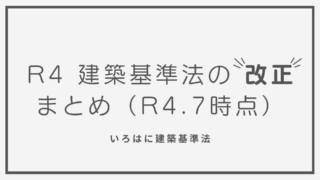ポリカ屋根のカーポート(自動車車庫)は設置場所などの条件によって設置の可否が分かれます。
今回はそんなポリカ屋根のカーポートに関するよくある疑問に答えつつ、設置の可否について解説します。
下記のような前提条件での解説とさせていただきますのでご注意ください。
- 屋根の材料:ポリカーボネート板
- 構造:アルミニウム合金造(いわゆるアルミ)
- 床面積:150㎡未満(1台あたり床面積約15㎡程度)
- 外壁:外壁はなく外気に開放されている
いわゆる4号建築物(法6条1項一号から三号に該当しない建築物)で、戸建の住宅に附属して設置されるようなカーポートを想定しています。
ポリカ屋根が使用できないケースの代替案についても少し解説します。
そもそも建築物か?
建築物です。屋根・柱があり、屋根の下に自動車を駐車するという用途がありますので建築物です。詳しくは以下で解説しています。
https://f-kenkihou.com/2022/05/18/kentikubutu/建築確認申請は必要か?
必要なケースと不要なケースがあります。
下記の表を確認ください。

- 防火地域・準防火地域 ▶ 建築確認必要
- 防火地域・準防火地域以外の都市計画区域等は床面積10㎡の増築・改築・移転 ▶ 建築確認不要
- 都市計画区域等外 ▶ 建築確認不要
※ 上記の「都市計画等」とは、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区、都道府県知事が指定する地域です。詳細は建築基準法6条1項四号を確認ください。
防火性能は?
主に3つの規定による制限を確認する必要があります。
- 屋根の性能(法22条、法61条)
- 開口部の措置(法61条)
- 内装制限(法35条の2)
この防火性能の観点がポイントです。そして複雑です。今回の解説では結論と簡単な解説にとどめます。
上記3つの制限による設置の可否を表にしました。設置できる場合でもポリカの防火性能に制限があるケースがあります。詳しくは下記で解説しています。

今回の解説の前提としている外壁のないカーポートについては、法84条の2(簡易な構造の建築物(開放的簡易建築物))の規定を適用することで防火・避難関係の一部の規定が適用除外とすることができます。
一部の規定について、開放的簡易建築物を適用して除外する事はできません。建築物(建築物の部分)として適用する・適用しないを決める必要があります。
屋根を不燃材料にすると使用範囲が広ります
ただ、屋根をポリカでなくアルミや金属板などの不燃材料とすることで設置できる範囲が広がります。

1. 屋根の防火性能は?
面積や設置場所によって必要なポリカの性能が異なります。そもそもポリカ使用不可(設置不可)の場合もあります。
表にまとめました。

表に出てくるDW、UWについては、法22条、法62条の規定により求められるいわゆる飛び火の構造(認定)と言われるものです。飛び火構造は、性能等の違いにより、DR、DW、UR、UWの4種があり適切に使い分ける必要があります。
法82条の4の簡易な構造の建築物(開放的簡易建築物)とする場合は、延焼のおそれのある部分にポリカの屋根を設けることはできません。不燃材料なら可。
法82条の4の簡易な構造の建築物(開放的簡易建築物)としない場合は、飛び火構造の規定(法22条、法61条)により床面積30㎡超はポリカの屋根を設けることはできません。
それ以外の場合でも認定品やJIS規格品のポリカとしなければならいケースもありますので注意が必要です。
屋根を不燃材料
屋根を不燃材料とした場合、他の規定で特別な制限がない限り、屋根の防火に関する規定により制限を受ける事はなくなります。もちろん、後述する開口部の制限や、内装制限についての規定は別途クリアする必要があります。
防火性能の比較
屋根の防火性能に関する規定を正しく理解するためには、ここででてくる材料の防火性能について優劣をイメージできるとわかりやすくなります。

飛び火構造(飛び火認定)の防火性能は準不燃材料より劣ります。
性能上、DR認定≒UR認定、DW認定≒UW認定だと思われます。規定上はUR認定が使用できれば代わりにDR認定を使用することもできますが、DR認定が使用できるからといって必ずしも代わりにUR認定を使用することができません。(一部、私の知識不足なところがあり推測(見解)です…。)
2. 開口部の措置は?
設置場所によって、延焼のおそれのある部分にカーポートを設置する場合に防火設備の設置が必要です。防火設備が必要となった場合には、外壁がなく外気に開放されていることが基本のポリカのカーポートは設置できません。
開口部の措置(防火設備の要・不要)について、表にまとめました。

法82条の4の簡易な構造の建築物(開放的簡易建築物)とする場合は、延焼のおそれのある部分に設置しても開口部の防火設備の設置は不要です。ただ、延焼のおそれのある部分にはポリカの屋根は設置できません。屋根を不燃材料とすれば可。
3. 内装制限は?
簡易な構造の建築物(法82条の4)を適用する場合、内装制限は免除されますが、適用しない場合は原則内装制限が適用されます。
内装制限について、表にまとめました。

そもそも外壁がないため壁には内装制限は適用されませんが、天井については屋根があるため適用されます。カーポート(自動車駐車場)の天井は準不燃材料で仕上げなければなりません。よって、準不燃材料より防火性能の低いポリカは不可です。
また、内装制限は用途が自動車車庫であるため制限を受ける(令第128条の4第1項第二号)のですが、床面積30㎡以下の自動車車庫については建設省の通達(昭和36年1月14日付住発第2号)により自動車駐車場と扱わないとされています。よって、床面積30㎡以下の自動車車庫については内装制限の適用を受けません。
法82条の4の簡易な構造の建築物(開放的簡易建築物)とする場合は、内装制限の規定の適用が除外されます。
30㎡以下は自動車車庫として扱わなくてよいという通達により内装制限の適用を受けません。
構造は?
構造(構造耐力関係規定)については法20条1項四号イを適用するのが原則です。カーポートを商品として販売しているメーカーのものであればほとんど法20条1項四号1イを適用するものだと思われます。
法20条1項四号イを適用する場合、仕様規定(令3章1節〜7節の2)の規定を満たすことで、構造計算(令3章8節)は不要です。
ただし基礎については注意が必要です。
独立基礎であることが多く、令38条4項の構造計算で構造上の安全を確認する必要があります。いわゆる「但し書き計算」と言われるもので令3章8節の一連の構造計算とは異なります。
4号特例も適用できます。
法20条1項四号イを適用する場合、4号特例が適用でき、建築確認において構造図の添付が不要です。
基礎部分について、上記の令38条4項の「但し書き計算」をした場合であっても、4号特例を適用することができます。
構造を鉄骨造・木造とした場合は?
鉄骨造の場合は、アルミ造の場合と防火規定・構造規定ともにほぼ同様に考えることができます。
木造の場合は注意が必要です。
法82条の4の簡易な構造の建築物(開放的簡易建築物)の適用ができません。その場合、防火地域・準防火地域では屋根を不燃材料としても設置できません。その他の地域でも床面積30㎡超の設置はできなくなります。また、30㎡以下の場合でも法22条、法62条の飛び火構造が適用される場合は、柱・梁を準不燃材料以上とすることが求められますので設置できません。
まとめ
そもそも、設置できるかどうかは、防火性能に関する3つの制限をクリアできるかどうかにかかってきます。そして、3つの制限をクリアするために法82条の4で規定する簡易な構造の建築物を適用するかどうかも大きなポイントです。
設置場所、規模などに応じて考えていく必要があります。そして、時にはポリカ屋根でなくアルミや鋼材といった不燃材料の屋根とすることで解決できる場合もあります。
私が参考にしている本
私がいつも参考にしている本です。表や図が多くわかりやすい参考書です。ただ建築基準法に不慣れな方にとってはまだまだ、専門用語が多く理解に苦しむ方も多いと思います。もちろん私もその一人です。本サイトがそういった方に建築基準法やこれらの参考書との架け橋としての役割を担っていけば幸いです(*ᴗˬᴗ)⁾⁾ペコ