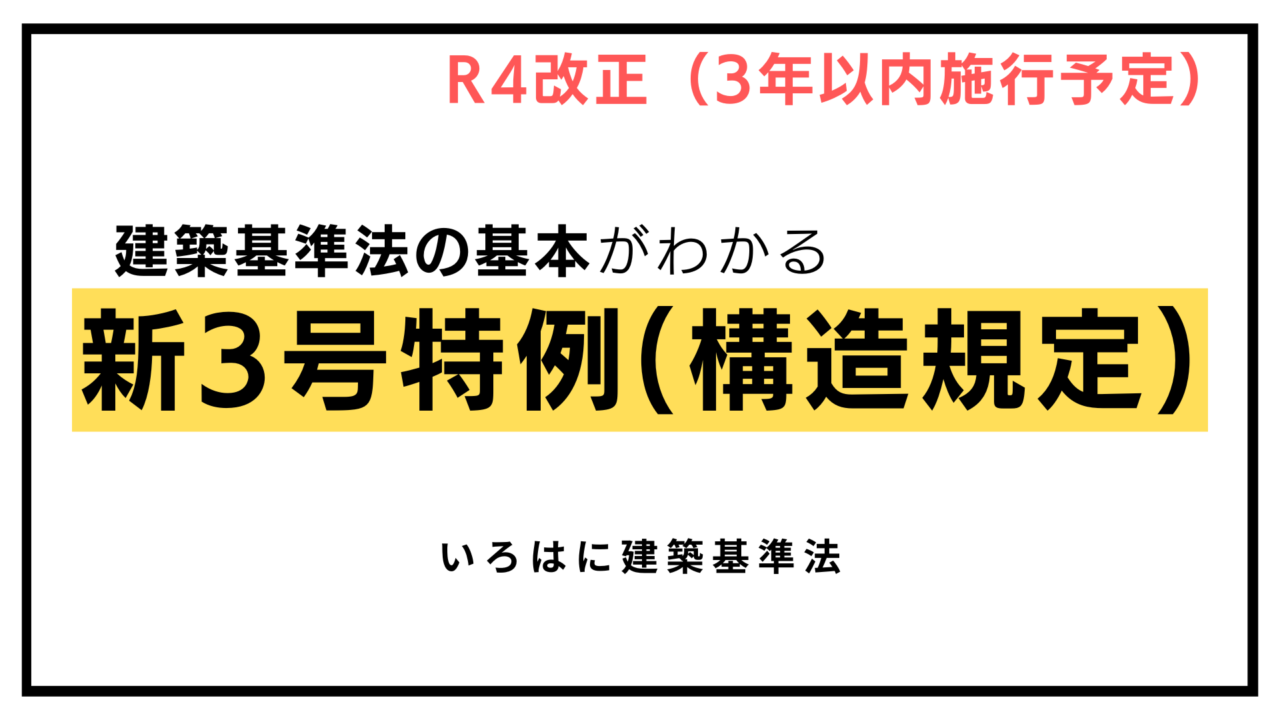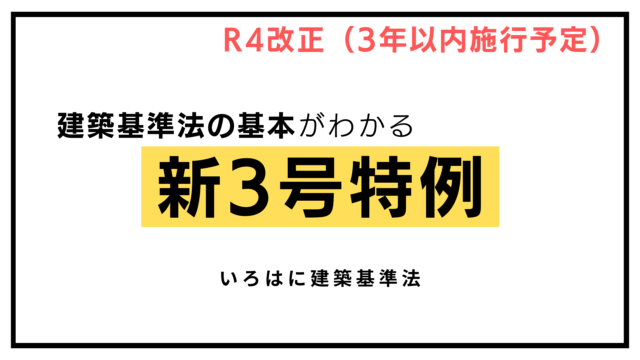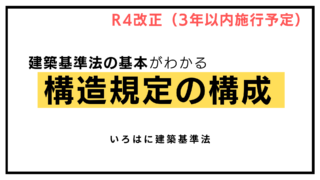本解説は★R4改正(3年以内施行予定)に対応した内容で、R6.4.1時点では未施行ですのでご注意ください。
【はじめに】
建築基準法は、法令集を読むだけでは理解できない規定が多々あり、誰しも次のような経験をしたことがあると思います。
- 読解するのに時間がかかる。
- 途中で読解をあきらめる。
- 誤解する。
これらを解決できるよう建築基準法に慣れていない方でも短時間で正しく理解できる内容となることを目標として記事を作成しています。特に、次のような方に読んでもらえると嬉しいです。
- 1級建築士試験などの建築基準法に関する出題のある資格試験勉強中の方
- 建築基準法が苦手な実務者
- 建築基準法を勉強したい建築初心者
建築士試験の勉強中の方や実務者は、建築基準法をみながら解説を読み進めてみてください。
新3号特例について
法第6条第1項第3号に該当する建築物(3号建築物)は、建築確認・完了検査において、一部の規定の審査・検査を省略することができます。このことを新3号特例と言います。
新3号特例(旧4号特例)の基本の解説は次の記事で解説していますのでご確認ください。(R4改正(3年以内施行)対応)
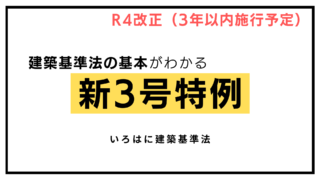
R4改正(3年以内施施行)の要点
この改正によって旧4号特例で特例の対象だった木造建築物の一部が新3号特例では、特例の対象外となりますので注意が必要です。
| 旧4号特例対象 の木造建築物 | 次のいずれかに該当する木造建築物 階数2以下、延べ面積500m2以下、高さ13m以下、軒高さ9m以下 |
| 新3号特例対象 の木造建築物 | 次のいずれかに該当する木造建築物 階数1、延べ面積200m2以下 |
構造規定の新3号特例の概要
構造規定の特例対象となる規定は、たの規定と同様に法第6条の4第3号・第4号に基づき、令第10条3号・4号で規定されています。建築場所・用途により第3号と第4号に分けて規定されていますが、構造規定については、どちらでも同じです。
ただし、構造規定については、次の条件を満たす建築物でなければ構造規定の特例を適用することができません。
- 仕様規定を適用する建築物であること(条件1)
- 令第80条の2の特殊の構造方法の建築物については、H19国交告第1119号第1号〜第4号で指定された基準を適用する建築物であること(条件2)
(注)構造規定とは法第20条(構造耐力)に基づく規定のことで、構造規定のほか構造耐力関係規定、構造関係規定などと言われています。
(条件1)仕様規定を適用する建築物
構造規定(法第20条)については、令10条第3号・第4号の条文にカッコ書きがあり「法20条(第1項第四号イに係る部分に限る。)」と規定されています。
構造規定の基本ですが、新3号建築物は構造規定の適用について法第20条第1項第4号に規定されており、法第20条第1項第4号のイ(構造計算基準が適用されない)かロ(構造計算基準が適用される)を選択することができます。
そして、新3号特例が適用できるのは、構造計算基準が適用されない法第20条第1項4号イの規定を適用する建築物だけで、構造計算基準が適用される法第20条第1項4号ロについては適用できません。
| 法第20条第1項第4号 | 新3号特例の適用 |
|---|---|
| イを適用する建築物 | ○ |
| ロを適用する建築物 | ー |
(条件2)特殊の構造方法(法第80条の2)
特殊の構造方法とは、令第3章第3節〜第7節までの一般的な構造方法以外の構造方法のことで、構造方法ごとに告示で仕様規定や構造計算基準が規定されています。R6.4現在は17の告示で規定されています。
そして、新3号特例が適用できるのは、次の4つの構造方法だけです。令第10条第三号ロ・第4号ロに基づきH19国交告第1119号で規定されています。
- プレストレストコンクリート造(S58建告第1320号第1〜第12)
- 壁式鉄筋コンクリート造(H13国交告第1026号第1〜第8)
- 型枠壁工法・木質プレハブ工法(H13国交告第1540号第1〜第8)
- アルミニウム合金造(H14国交告第410号第1〜第8)
よって、17ある特殊の構造方法の中でも上記以外の膜構造建築物(H14国交告第666号)などの建築物には適用できません。
最後に
建築基準法は、慣れが必要です。逆に言うと、慣れてしまえばこれまで読んだことのない条文でも、自力で読解することができます。自力で読解できるようになると建築基準法を読解することが楽しくさえなります。
【step①】
- 解説を読む ▶︎ 条文を確認する ▶︎ 理解できる
【step②】
- 条文を読む ▶︎ 解説で確認する ▶︎ 理解できる
【step③】
条文を読む
▼▼ フォローしていただけると嬉しいです ▼▼